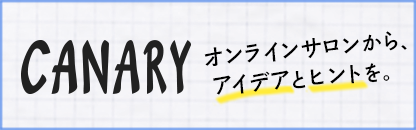作家・猪瀬直樹の脳内。「【前編】史実に迫るための取材学と文献学」では、史実・真実に迫るために自身が心がけていること、行っていることについて詳細に語ってもらった。
後編では、いよいよ史実や真実に迫るために綿密な取材や調査を行う猪瀬直樹が、なぜ「小説」という表現形態にこだわるのか。その哲学に迫っていきたい。

「物語だから、小説として読めるようにしなくちゃいけない。小説といっても、本当のことしか書かれていないわけだけど。真実だからって『ノンフィクション』と銘打って、ただ調べて書きましたってそのまま出すだけでは、全然おもしろくないんだよね。」
猪瀬直樹のことを「ノンフィクション作家」であると言う人もいる。しかし、周囲がどう呼称しようと、本人の中で「小説」と「ノンフィクション」は明確に違うものであるようだ。
猪瀬にとって小説とは、面白く読むことのできるものだ。『昭和16年夏の敗戦』を例にとって、読者を物語に没頭させ、面白く読ませる小説の構成について語ってくれた。
「『昭和16年』だったら、まず現在において、『僕』が『模擬内閣』で総理大臣を務めていた窪田角一さんと共に、総力戦研究所跡地へ行く。そこで読者に『総力戦研究所なんてものが本当にあったのか?』という疑問を持たせるんだ。いきなり「総力戦研究所」というものが存在した事実や、その説明をしはじめても仕方がない。物語の始まりには驚きがあった方がおもしろいに決まっている。こういった構想力がないとダメだよ。誰かに読んでもらいたいわけだから。
そこからパッと場面が切り替わって『昔』が描かれる。場面の時制が変わると、黒澤明『七人の侍』のオープニングのように登場人物が方々から集まってきて、知らない人同士が出会うという『物語』が始まる。そうして「総力戦研究所」なるものの全景が徐々に浮かび上がっていく中で、「日本必敗」の結論を実際の内閣に報告することになる「模擬内閣」が立ち上がっていく。」
私たちがすらすらと読み進めていく文章に、考え抜かれた小説としての構成があることがわかる。猪瀬直樹が小説に施す仕掛けは、たとえば「僕」という一人称にも仕掛けられている。猪瀬の小説には、「僕」が資料を見つけたシーンや、「僕」が実際にインタビューを行った際の描写が頻出する。猪瀬作品における「僕」の役割とはいったい何なのだろうか。
文化人類学者で東大名誉教授である船曳健夫は、猪瀬作品の「僕」は「現在という時点から全体を見渡せる立場でとらえられる、客観的で総合的」な語り手であると同時に「時間を自由に動く」存在だと要約している。
「『僕』は、多くのすでに亡くなっている人たちが作りだした歴史とドラマを読み解き、それを私たち読者に語りかけます。いわば読者との対話になっています」と船曳が書くように、猪瀬作品の「僕」は、物語の「道案内」役として機能している。
「司馬遼太郎さんの作品だって読んでると突然『自分』が出てくる。いきなり『私は思った』とかなんとか書かれているんだよ。そういう自由な書き方があっていいわけだよね。いかにも『小説です』って書く必要はないけど……。小説にもいろんな形があるからね。」

自分を知るための読書
猪瀬作品を駆動させるのは「僕」であり、「僕」はある疑問を持ってそれを読者と共に解き明かしていく。「僕」の疑問が、あらゆる物語の起点だ。
「人間は生きている限り毎日疑問を持つわけだ。そうだろう? たとえば毎年8月15日「終戦記念日」を迎えるたびに、メディアは「日本は戦争で悪いことをしました」と語る。しかし、そもそもなんで戦争を始めたのだろう、という疑問を持つ。だってどう考えても勝てるわけないんだから。おかしいでしょう。そして戦前にも自分と同じように「おかしい」思った人がいるに違いない、と仮説を立てる。
調べてみると、当時生きていた人も『おかしい』と思っていたということが分かるんだよ。『ちょっと変だよなあ』と感じている。国民全員が『天皇陛下万歳』と叫んで戦争をはじめようとしていたわけじゃない。政府には頭脳明晰な人たちがいたのに戦争は始まった。結局、開戦は当時の国際情勢と大日本帝国のシステムによって、流れで決まったことだ。そして、いちど決定的になった流れを食い止めるのは難しい。
『自分』の生きている現代と、あの時代は変わらないと思ったほうがいい。いつの時代も人間は皆同じことを考えているわけだから、戦前の奴らは皆頭が悪かったなんていうことはないんだよ。」
猪瀬作品における「僕」はいつも疑問を持っている。それは、現実を生きる私たちだって同様のはずだ。しかし、日々漫然と生きてしまっている私たちは、なかなかその疑問に対して自覚的になることは少ないだろう。私たちが日々生きる中で感じている「疑問」とは、そもそもなんだろうか。
そんなぼんやりした質問をすると、猪瀬は、すべての人間にとっての疑問とは、「自分の存在」だと語ってくれた。
「誰もがそうだけど、『自分』というのは空間と時間のなかにいるわけだよね。つまり『自分』が抱く疑問っていうのは、広大に広がる空間と脈々と続く時間のなかで生まれる。つまり、「世界」と「歴史」のなかで疑問は生まれているんだ。そこに位置づけられる『自分』が持つ疑問というのは「半径3メートル」の話ではないんだよ。
たとえばNHKに「ファミリーヒストリー」って番組があるだろ? あの番組のように「自分の親父はサラリーマンだったけど、じいちゃんはお店をやっていた。さて、何を売ってたんだっけな」とか不思議に思うことってあるじゃない。もっと先のひいおじいさんとかまで含めて3世代、4世代先まで自分の「ルーツ」を探っていく。彼らと自分はどういう関係なんだろうか、と考える。
人は自分がいまここにいる必然性というか、運命を考えてしまうものなんだよ。たとえ一卵性双生児として生まれても、出会う人間や育っていく環境によって、ふたりは全然異なる人間に育っていく。人間はそういうものなんだよね。誰にでも、その人固有の物語がある。自分の存在に関わるすべてが物語なんだよ、すべてが。つまり、すべては小説なんだ。」

猪瀬は時間のなかに「自分」を位置づけるうえで、「古典」を読み歴史を学ぶことが大切だと言う。それは、古典が湛える一見遠いようにも思える時間と空間を、今を生きる「自分」と接続する試みだ。「古典」は「自分」という小説のスケールを大きくしてくれるツールなのかもしれない。
ただ、猪瀬の言う「古典」というのは、一般に考えられているそれとは少し異なるようだ。
「『古典』といっても何も『源氏物語』を読めってことじゃない。『自分』が生まれるよりも前の時代に書かれた作品はぜんぶ『古典』なんだよ。自分が生まれてから書かれた文章は、実感を持って読めるけれど、生まれる前のできごとには実感が伴わない。最初は実感が伴わなくても良い。でも、古典の時代と『自分』の今いる現在とが、どんなふうに関係しているかを考えながら読んでいくんだ。そうすると過去の時代が自分の頭のなかの環境の一部になっていく」
猪瀬直樹がSynapseで「近現代を読む」というテーマで教養塾を主宰する理由もここにある。最後に、猪瀬に近現代を読むことで得られる「知性」「教養」はどのように私たちの生活を変えると思うかを尋ねると、少し厳しい応答が返ってきた。
「生活や仕事に役立つとか、そういう実感が『知性』というわけじゃないんだよ。実感だけしかないなら、動物と何も変わらないよ。実感で喋っているうちは動物なんだ。何かに触れたときに『キモい』とか『楽しい』とか『おもしろい』とか言っているうちは女子高生といっしょ。実感ってのはさ、形容詞で終わっちゃうんだ。一方で実感を持てない世界、つまり『古典』(=『自分』が生まれるよりも前の世界)を自分の頭のなかで再構成できれば、『今』をも再構築することができる。その創造力や構想力こそが『リベラル・アーツ』、つまり教養ということだよ」

今ここに在る自分の疑問を起点に、過去を知り、再構成する。それが猪瀬直樹の書く「小説」だ。それは史実に基づいた作品であるにも関わらず、今を生きる私たちが見る世界を変容させる力を持つ。
猪瀬氏が「小説」という表現形態にこだわる理由と、それを支えるクリエイティビティの源泉を垣間見た気がした。