子供の栄養〜発達障害〜
テキスト
- 内容
- ライブラリ
はじめに
ビタミン
ビタミンA
ビタミンK
ビタミンB2
ビタミンB6
ミネラル
■鉄
■マグネシウム
■亜鉛:
■銅
■動物性たんぱく
■質の良い油
発達障害の治療
発達障害の治療
1. ビタミンB群の役割と発達障害への影響
2. オメガ3脂肪酸の役割と発達障害への影響
3.プロバイオティクスの役割
発達障害と栄養療法の統合的アプローチ
フォローしたサロンの情報を、ご登録のメールアドレスにお届けします。
サロンをフォローする
-
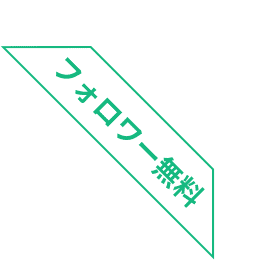
医療の闇Ⅱ 〜薬や健康食品の闇〜
【薬は飲まない】 薬を飲んでも、無害ならばまだよいのです。 薬には副作用があります。副…
テキスト
-
オンラインサロン2026年
みなさま、お待たせいたしました!! 2026年 オンラインサロン年間講義スケジュール 全期…
テキスト
-

新サロンのご案内!!
新オンサロURLはこちら‼️ 新しく以下のサロンをオープンしました。 https://lo…
テキスト
-

いよいよナノカプセルビタミンC販売開始!!
私のビタミンCローションがさらなる進化を遂げて登場。 ついに世界初のビタミンCの原液をナノ…
テキスト
-
全ての眠れない方へ
運動と睡眠:からだの生理・行動・環境を一つに束ねる“眠りの設計図” 目次運動と睡眠:からだ…
テキスト
-

831講演会
動画
-
ファイトケミカルの最新情報!!
はじめに わたしのフォロワーさんはすでにたくさんのファイトケミカルを日常に取り入れていると…
テキスト
-

環境と炎症が現代型糖尿病のもと
環境と炎症が現代型糖尿病のもとトランス脂肪酸・マイクロプラスチック・PFAS、そして腸内バ…
テキスト
-

過度な筋トレは禁もつ!!
近年の筋トレブームで男女問わず、筋トレに励んでいる人がジムでも増加しているのが見て取れます…
テキスト
-
筋トレが人生を変える —“最強の処方箋”
筋トレが人生を変える医学的理由 「筋トレ」はもはや当たり前のように行っているのではないでし…
テキスト
-
【食品添加物危険度ランキング:科学的根拠と最新情報】
はじめにみなさまはどれくらいの添加物を摂取していると思いますか??日本人の年間の食品添加物…
テキスト
-

玄米酵素のすごさ!!
玄米酵素FBRAとポストバイオティクス みなさん、お疲れさまです。先日講義させていただいた…
テキスト
-

私の飲んでいる肌におすすめのサプリ5選!!
【科学的根拠に基づくサプリメント】 みなさまが飲んでいるほとんど何の効果もないサプリメント…
テキスト
-
化粧品につかわれる危険物質!!
はじめに 化粧品は日常生活において広く使用されていますが、その成分には健康や環境に悪影響を…
テキスト
-
中医学とアーユルヴェーダ
アーユルヴェーダと医療 1. アーユルヴェーダの基本概念 • 語源: …
テキスト
-

間違えだらけの医療―何が正しいのか―
間違えだらけの医療―何が正しいのか― 放射線や抗がん剤、天然成分の効果と自然治癒力 はじめ…
テキスト
-

自由と自然への畏敬 〜ヘンリー・デイヴィッド・ソローの思想〜
自由と自然への畏敬 〜ヘンリー・デイヴィッド・ソローの思想〜 目次自由と自然への畏敬 〜ヘ…
テキスト
-
老化とは〜最新研究から〜
目次 表皮幹細胞とはターンオーバーのプロセス表皮幹細胞と自然老化の関係老化への対策と研究動…
テキスト
-
添加物の闇
添加物の闇 はじめに 現代の食品産業は、便利さと効率を追求する一方で、私たちの…
テキスト
-
医師が教える「殺菌、除菌があらゆる病気の原因」
医師が教える「殺菌、除菌があらゆる病気の原因」 はじめに 現代社会では、殺菌・除菌が健康維…
テキスト
オンラインサロン情報
予防医療大学院
サロン紹介
- 運営ツール
- DMMオンラインサロン専用コミュニティ
 お気に入り
お気に入り

 購入済み情報
購入済み情報